alter. Talks
alter.会期中、会場では計6つのトークセッションを開催。いまプロダクトデザイナーが直面する問題から鑑賞者/ユーザーのクリエイティビティ、プロダクトデザインのフロンティアに至るまで、多彩なゲストとともに現代のプロダクトデザインを巡る問題系を浮き彫りにしていきます。
注意事項
トークは公開収録型イベントとして実施いたします。セッションの模様は、会期後に音声配信として公開予定です。
会場内にはご着席いただける席数が限られております。
座席はごくわずかとなりますため、立ち見となる場合がございます。
事前予約は受け付けておりません。すべて当日先着順でのご案内となります。
混雑状況により、安全確保のため入場を制限させていただく場合があります。
その際は、その場でのご観覧をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。
セッション中の録音・録画・撮影はご遠慮ください。
公式の記録・配信スタッフが入る場合がございます。
DAY1_ プロダクトデザインの現在地
いまプロダクトデザインはどんな環境に置かれているのか?グローバルな問題系からつくり手と受け手の応答、さらには新興市場のオルタナティブな動きをたどりながら、現代デザインのエコシステムを考える。
SESSION1-1
いま、アジアの美を考える。
2025.11.07 (Fri) 16:00-
石川俊祐 × Meng Jinhui × Danny Wicaksono × 古屋言子
「美」とは何でしょうか。それは形や装飾ではなく、生き方や世界の見方に宿るものでもあります。これまでは西洋的な価値観に照らされてきた“アジアの美”を、いま改めて自らの感性から見つめなおすために──インドネシアや中国から来日中のクリエイターを招き、KESIKI INC.の石川俊祐とD&AD リージョナルマネージャーの古屋言子とともに、文化も時代も超えた「美」の再定義を試みます。
TICKETS石川俊祐

Meng Jinhui

Danny Wicaksono

古屋言子

SESSION1-2
これからのデザインシーンはどこにあるのか
2025.11.07 (Fri) 18:00-
alter.参加クリエイター
今回のalter.には、1990年代以降に生まれた若手クリエイターも多く参加しています。狭義のプロダクトデザインに留まらず領域横断的に同世代のクリエイターとコラボレーションを重ね、商業的な実践にも取り組む彼/彼女たちは、これからのデザインシーンやデザイナーの役割をどう捉えているのでしょうか。多くのクリエイターが登壇し、ラウンドトークを繰り広げます。
TICKETSalter.参加クリエイター
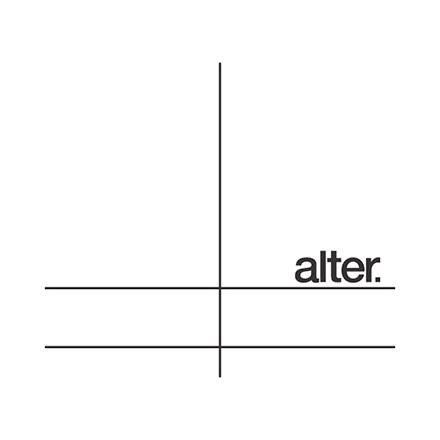
DAY2_ 個と向き合うためのデザイン
プロダクトデザインの営為とは、常につくり手・受け手の「個」とともにある。つくり手の強いエゴから創造性が生まれることもあれば、受け手のクリエイティビティとの相互作用が生まれることも、受け手がつくり手へと回ることもある。果たして現代のプロダクトデザインは「個」とどう向き合っていけるのか。
SESSION2-1
受け手のクリエイティビティを拡げる
2025.11.08 (Sat) 13:00-
杉野龍起 × 福井裕孝 × GAKU
デザインやクリエイティビティとは、つくり手だけのものではありません。鑑賞者やユーザーといった受け手もまた、クリエイティビティの担い手と言えます。クリエイションのプロセスに着目しさまざまな活動を展開するDODIと、モノと人の関係を問う演劇作品をつくる演出家の福井裕孝、「使い手の創造性」を問うワークショップに参加してきた10代のGAKU受講者とともに、受け手のクリエイティビティの拡げ方を考えます。
TICKETS杉野龍起
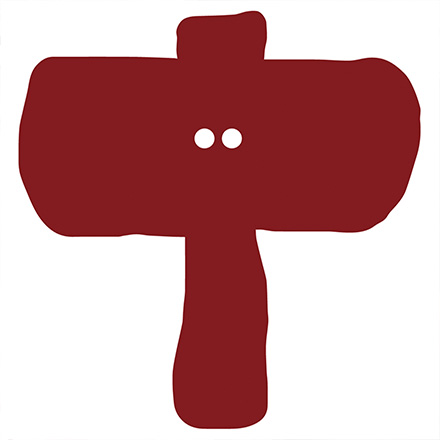
福井裕孝

GAKU

SESSION2-2
根源的欲求から始まるプロダクトデザイン
2025.11.08 (Sat) 15:00-
松本光一 × 太田琢人
人々の生活を変えるプロダクトは、人間の根源的欲求から生まれるもの。なかでもTENGAの創業者・松本光一は、人間の「性」へ徹底的に向き合うことで社会のタブーや固定観念を突き破るプロダクトを生み出しました。同時に松本はデザインの原動力に他者の喜びを見出してもいます。デザイナーをものづくりに向かわせるものは一体なんなのか? alter.出展者でもありさまざまな試行錯誤を続けるアーティストの太田琢人とともに、ものづくりの根源へと立ち返ります。
TICKETS松本光一

太田琢人
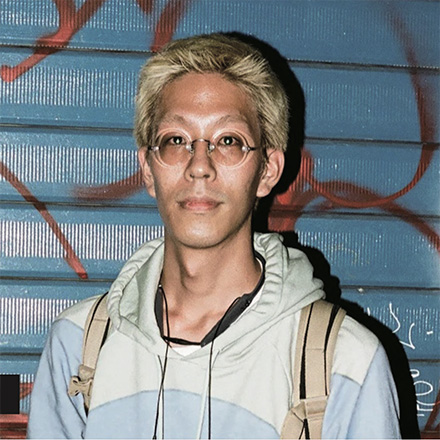
DAY3_ フロンティアをデザインする
プロダクトデザインの領域は常に広がっている。欧米のみならず中国をはじめとするアジア圏の台頭やデジタルテクノロジーによる新たなインターフェースの登場、さらには今回のalter.出展プロジェクトから見える新たな可能性まで──プロダクトデザインのフロンティアを巡る。
SESSION3-1
修理する権利、改造する自由
2025.11.09 (Sun) 13:00-
吉田健彦 × 長澤智美
プロダクトとはデザイナーが一方的にそのあり方を規定するものではなく、しばしばユーザーとの関わりのなかでその姿を変えていきます。欧州で法制化が進む「修理する権利」に精通する研究者/エンジニアの吉田健彦と、数々のエンジニアたちが改造を通じて異形のプロダクトを生み出すテレビ番組『魔改造の夜』のプロデューサーを務める長澤智美とともに、修理や改造など、ユーザーがプロダクトへ主体的に介入する営為から生まれるクリエイティビティを考えます。
TICKETS吉田健彦

長澤智美

SESSION3-2
拡張するインターフェース
2025.11.09 (Sun) 15:00-
布施琳太郎 × 小山虎
パソコンのGUIから始まりスマホ、ヘッドマウントディスプレイに至るまで、新たなインターフェースは新たな体験を生むだけでなく、常に人間が世界を認識する方法をも更新し、人とモノの関係性を変えてきました。近年インターフェースに関心を寄せるアーティストの布施琳太郎と、コンピュータ史に精通する小山虎とともに、拡張しつづけるインターフェースからどんな可能性が生まれるのか問うていきます。
TICKETS布施琳太郎
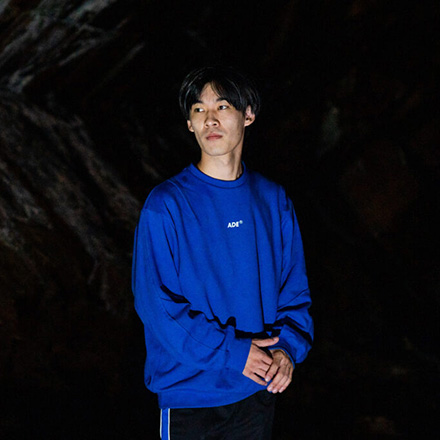
小山虎

Opening Session
いまここにある課題へ応答するために
2025.11.06 (Thu) 18:00-
Tanja Hwang × Olivier Zeitoun × Kristen de La Vallière × 中村圭佑 × Simone Farresin(TBD)
気候変動や国際情勢の変化、生成AIをはじめとする新たなテクノロジーの登場──急速に社会が変化していくなかで、「デザイン」を取り巻く環境も日々揺らいでいます。果たしていまデザインが直面する課題とはなんなのか。alter.のコミッティメンバーとともに、現代のデザインが置かれた環境を明らかにします。セッション内ではコミッティメンバーによるアワード受賞作品も発表予定。 *クローズド開催となりますが、後日音声配信いたします。
TICKETSTanja Hwang

Olivier Zeitoun

Kristen de La Vallière

中村圭佑

Simone Farresin *TBD
